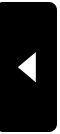2018年09月09日
活版印刷三日月堂 その3
活版印刷三日月堂(第三巻 庭のアルバム)
著者 ほしおさなえ

引き続き三日月堂と弓子さんに登場する人たちが、なんらかの関わりを持って行く。
当然媒介するものは、活版印刷ですね。
のちに三日月堂を手伝うようになる、自分に自信のない高校生の楓。
なによりも弓子さんのことを、仕事もことも含めてわかってくれる、分かり合えるパートナーの登場です。
1.チケットと昆布巻き (第三巻 第一篇)
月刊めぐりんの編集者、俺(竹野くん)と川越の街および三日月堂との邂逅の物語。
片山慎一さんが企画した『我らの西部劇』の取材がきっかけとなり、三日月堂の弓子さんと知り合う。
入場チケットの印刷のデザインを手伝うなどするうち、弓子さんを意識するようになり・・・。
兄への屈折した感情、自身の仕事への疑問など弓子さんの生き方に触れることで、繰り返した自問への回答を得る。
2.カナコの歌 (第三巻 第二編)
弓子さんの母親、(旧姓村田)カナコさんの友人であったわたし(聡子)と同じく友人だった裕美の物語。
わたしは結婚はしておらず、両親の介護をきっかけに仕事をやめ、川越に帰ってきた。
弓子さんが月刊めぐりんに出ていたことをきっかけに、わたしは三日月堂を訪れ、生前のカナコさんについて弓子さんと話す。
短歌を残していたカナコさんを偲ぼうと、わたしは裕美と短歌集をつくろうとする・・・。
弓子さんの母親の過去をめぐって、かつての友人が登場し弓子さんと関わってゆく・・・。
母、カナコさんの残され行く弓子さんへの想い、そしてそれを知る弓子さんの想い。
優しい友達たち、優しいまわりの人たち。切なくもやさしい一編です。
弓子さんのお母さんのことが分かる回。
3.庭のアルバム (第三巻 第三編)
ゼミで一緒だったカナコさんの友達の娘、楓さんの物語。
わたし(楓)は、写生が好きないつもスケッチブックを持ち歩く高校生だ。
母が持ち帰った短歌集が気になり、三日月堂に向かう。
祖母の家が更地になると聞き、森のような庭の植物を絵で残そうと植物カードの印刷を決心する・・・。
祖母や両親と心がつながってゆくこれも優しい一編です。
4..川の合流する場所で (第三巻 第四編)
本町印刷の技術部に所属する僕(島本悠生)と弓子さんの出会いの物語。
活版印刷のイベントを見るために大伯父とともにでかけたわたしは、三日月堂のブースで『我らの西部劇』と
楓とともに作成した植物カードを目にする。
三日月堂の動かない平台の話となり、本町印刷の本社(岩手)にある平台の機械に話が及ぶ。
弓子さんは岩手を訪れ、平台の稼働を目にする。
僕のお祖父さんが組んだ、八木重吉の詩集を印刷することになり・・・。
北上川の河原で、母を偲ぶ弓子さんとそれを見守る僕。
二人が知り合い、二人の距離が近くなる一編です。
著者 ほしおさなえ
引き続き三日月堂と弓子さんに登場する人たちが、なんらかの関わりを持って行く。
当然媒介するものは、活版印刷ですね。
のちに三日月堂を手伝うようになる、自分に自信のない高校生の楓。
なによりも弓子さんのことを、仕事もことも含めてわかってくれる、分かり合えるパートナーの登場です。
1.チケットと昆布巻き (第三巻 第一篇)
月刊めぐりんの編集者、俺(竹野くん)と川越の街および三日月堂との邂逅の物語。
片山慎一さんが企画した『我らの西部劇』の取材がきっかけとなり、三日月堂の弓子さんと知り合う。
入場チケットの印刷のデザインを手伝うなどするうち、弓子さんを意識するようになり・・・。
兄への屈折した感情、自身の仕事への疑問など弓子さんの生き方に触れることで、繰り返した自問への回答を得る。
2.カナコの歌 (第三巻 第二編)
弓子さんの母親、(旧姓村田)カナコさんの友人であったわたし(聡子)と同じく友人だった裕美の物語。
わたしは結婚はしておらず、両親の介護をきっかけに仕事をやめ、川越に帰ってきた。
弓子さんが月刊めぐりんに出ていたことをきっかけに、わたしは三日月堂を訪れ、生前のカナコさんについて弓子さんと話す。
短歌を残していたカナコさんを偲ぼうと、わたしは裕美と短歌集をつくろうとする・・・。
弓子さんの母親の過去をめぐって、かつての友人が登場し弓子さんと関わってゆく・・・。
母、カナコさんの残され行く弓子さんへの想い、そしてそれを知る弓子さんの想い。
優しい友達たち、優しいまわりの人たち。切なくもやさしい一編です。
弓子さんのお母さんのことが分かる回。
3.庭のアルバム (第三巻 第三編)
ゼミで一緒だったカナコさんの友達の娘、楓さんの物語。
わたし(楓)は、写生が好きないつもスケッチブックを持ち歩く高校生だ。
母が持ち帰った短歌集が気になり、三日月堂に向かう。
祖母の家が更地になると聞き、森のような庭の植物を絵で残そうと植物カードの印刷を決心する・・・。
祖母や両親と心がつながってゆくこれも優しい一編です。
4..川の合流する場所で (第三巻 第四編)
本町印刷の技術部に所属する僕(島本悠生)と弓子さんの出会いの物語。
活版印刷のイベントを見るために大伯父とともにでかけたわたしは、三日月堂のブースで『我らの西部劇』と
楓とともに作成した植物カードを目にする。
三日月堂の動かない平台の話となり、本町印刷の本社(岩手)にある平台の機械に話が及ぶ。
弓子さんは岩手を訪れ、平台の稼働を目にする。
僕のお祖父さんが組んだ、八木重吉の詩集を印刷することになり・・・。
北上川の河原で、母を偲ぶ弓子さんとそれを見守る僕。
二人が知り合い、二人の距離が近くなる一編です。
2018年09月09日
活版印刷三日月堂 その2
活版印刷三日月堂(第二巻 海からの手紙)
著者 ほしおさなえ

第2巻も読了。
今回の4編もそれぞれとても良かった。
それぞれの想い、経験が三日月堂に関係するお話に収斂してゆく。
都合8編(第1巻も4編)の中のそれぞれの登場人物が、ほかの編でも関連して登場して段々と知り合いの輪が大きくなってゆく。
(月野弓子さんの三日月堂のお仕事も、だんだんと増えて行きます。)
悪い人は出てこない。
周りの人の気持ちがわかる人ばかりだなぁ。
自分のことを深く考えることができる人ばかりだなぁ。
と思いました。
1. ちょうちょうの朗読会 (第二巻 第一篇)
カルチャーセンターの朗読講座(黒田敦子先生)に通う、4人の生徒の物語。
図書館司書のわたし(小穂)、小学校教師の三咲、遊園地勤務の遥海、英語教室の講師の愛菜たちは、黒田先生から
4人で大正浪漫夢通りにある蔵カフェ『kura』での朗読会をしてみないかと誘われる。
黒田先生とKura店主の渋沢さんとの打ち合わせで演目も決まり、プログラムの印刷の話となる。
『ひとつだけの活字』の縁で、三日月堂へ。
素敵な仲間と朗読と、そしてシンプルな活字でできたプログラム。
こころ温まる物語です。
2. あわゆきのあと (第二巻 第二篇)
ぼく(田口広太君(11歳))と亡くなった姉あわゆきの物語。
お父さんから、生まれて三日でなくなった自分の姉の話を聞き、姉の十三回忌に『ファースト名刺』をつくろうと
思い立つ。
中谷先生が三日月堂を知っていた関係で、広太君は弓子さんと知り合い・・・。
(中谷先生は、『ちょうちょうの朗読会』の三咲さんかな?)
『淡雪って春の雪でしょう?雪が消えたら春が来る。・・・』
家族の絆、人々の思いがつまった切ない物語です。
3. 海からの手紙 (第二巻 第三篇)
銅版画を学んでいたわたし(昌代)が、あわゆきのファースト名刺が気になって三日月堂へ。
同居していた幸彦と別れ、きっぱり銅版画をやめたはずの昌代だったが、三日月堂へ行ったことをきっかけに
また制作を開始する。
昔の恩師、内山先生に紹介された今泉版画工房に通いだす。できた版画を弓子さんとみているうちに二人で
豆本にしてみようということになり・・・。
自身の悩み、師の友人の苦悩などそれぞれが向かい合いけじめをつけてゆく・・・。
応援したくなる短編です。
4. 我らの西部劇 (第二巻 第四篇)
心臓発作で倒れたわたし(片山慎一さん)が、結局会社を辞め実家の川越に移り住む。
働き手である私が倒れ、妻や子供たちに負担がかかる家庭でのいざこざのなか、父、片山隆一の晩年の仕事
がクローズアップされる。ライターとして死ぬ寸前まで仕事をしていた父には、未完の雑誌の最後の部分である
不明となっていた原稿があった。
その原稿を発見し、父の遺志を継いで、弓子さんの協力で本を作成する・・・。
親とは、子とは、家族とは、と問いかける短編です。
著者 ほしおさなえ
第2巻も読了。
今回の4編もそれぞれとても良かった。
それぞれの想い、経験が三日月堂に関係するお話に収斂してゆく。
都合8編(第1巻も4編)の中のそれぞれの登場人物が、ほかの編でも関連して登場して段々と知り合いの輪が大きくなってゆく。
(月野弓子さんの三日月堂のお仕事も、だんだんと増えて行きます。)
悪い人は出てこない。
周りの人の気持ちがわかる人ばかりだなぁ。
自分のことを深く考えることができる人ばかりだなぁ。
と思いました。
1. ちょうちょうの朗読会 (第二巻 第一篇)
カルチャーセンターの朗読講座(黒田敦子先生)に通う、4人の生徒の物語。
図書館司書のわたし(小穂)、小学校教師の三咲、遊園地勤務の遥海、英語教室の講師の愛菜たちは、黒田先生から
4人で大正浪漫夢通りにある蔵カフェ『kura』での朗読会をしてみないかと誘われる。
黒田先生とKura店主の渋沢さんとの打ち合わせで演目も決まり、プログラムの印刷の話となる。
『ひとつだけの活字』の縁で、三日月堂へ。
素敵な仲間と朗読と、そしてシンプルな活字でできたプログラム。
こころ温まる物語です。
2. あわゆきのあと (第二巻 第二篇)
ぼく(田口広太君(11歳))と亡くなった姉あわゆきの物語。
お父さんから、生まれて三日でなくなった自分の姉の話を聞き、姉の十三回忌に『ファースト名刺』をつくろうと
思い立つ。
中谷先生が三日月堂を知っていた関係で、広太君は弓子さんと知り合い・・・。
(中谷先生は、『ちょうちょうの朗読会』の三咲さんかな?)
『淡雪って春の雪でしょう?雪が消えたら春が来る。・・・』
家族の絆、人々の思いがつまった切ない物語です。
3. 海からの手紙 (第二巻 第三篇)
銅版画を学んでいたわたし(昌代)が、あわゆきのファースト名刺が気になって三日月堂へ。
同居していた幸彦と別れ、きっぱり銅版画をやめたはずの昌代だったが、三日月堂へ行ったことをきっかけに
また制作を開始する。
昔の恩師、内山先生に紹介された今泉版画工房に通いだす。できた版画を弓子さんとみているうちに二人で
豆本にしてみようということになり・・・。
自身の悩み、師の友人の苦悩などそれぞれが向かい合いけじめをつけてゆく・・・。
応援したくなる短編です。
4. 我らの西部劇 (第二巻 第四篇)
心臓発作で倒れたわたし(片山慎一さん)が、結局会社を辞め実家の川越に移り住む。
働き手である私が倒れ、妻や子供たちに負担がかかる家庭でのいざこざのなか、父、片山隆一の晩年の仕事
がクローズアップされる。ライターとして死ぬ寸前まで仕事をしていた父には、未完の雑誌の最後の部分である
不明となっていた原稿があった。
その原稿を発見し、父の遺志を継いで、弓子さんの協力で本を作成する・・・。
親とは、子とは、家族とは、と問いかける短編です。
2018年09月09日
活版印刷三日月堂 その1
読書記録です。
すてきな本にまた出合えました。
以下紹介です。
活版印刷三日月堂(第一巻 星たちの栞)
著者 ほしおさなえ

川越の街の片隅(鴉森稲荷神社の近く)にある活版印刷所のお話。
かつてその印刷所を営なんでいた祖父の後を継ぐことになった月野弓子さんと、周りの人達との心温まる短編集
(短編集と言っても語り手が変わりながら三日月堂にまつわる話の連鎖です)。
文章が落ち着いていて美しくわかりやすい。
登場する人達の心の動きが丁寧に描写されています。
宮下奈都さんの作品と同じような読後感でした。
(もう少しほっこりとした優しい感じかな)
続編が読みたくなる物語です。
1. 世界は森 (第一巻 第一篇)
三日月堂を再開することになったきっかけのお話。
わたし(市倉(旧姓藤山)ハルさん(川越運送店一番街営業所 所長))と、この春大学生になり家を出てゆく森太郎君の物語を軸に、
ジョギング仲間の、柚原さん(観光案内所のスタッフ)、大西君(大学院生、観光案内所のバイト)、葛城さん(ガラス店兼工房経営)
が登場。
ハルさんから森太郎君への卒業祝いである、名入りのレターセットのお話。
『名前って、不思議だな』・・・。
母子のきずなと、人々のやさしさに涙します。
2. 八月のコースター (第一巻 第二篇)
川越一番街のはずれで、喫茶店『桐一葉』を経営している僕(岡野まあ君)の話。
伯父から引き継いだ喫茶店の経営について、伯父の個性、自分の個性について悩む。
ハルさんから三日月堂のことを聞き、弓子さんとともに伯父の『短歌』を印刷したオリジナルコースターをつくる。
伯父はまあ君に俳句の手ほどきもしたことがあり、店名の桐一葉も高山虚子の句だった・・・。
まあ君は大学の俳句部に在籍していたことがあり、当時一緒にいた原田さんのことを思い出す。
伯父時代からの常連とのやり取りやまあ君の決意が胸に迫ります。
3. 星たちの栞 (第一巻 第三篇)
わたし(遠田先生、鈴懸学園の国語教師)と文芸部の生徒たち、村崎小枝、山口ゆう加の物語。
桐一葉でコース―たーを見た遠田先生が、生徒たちと三日月堂の見学に行く。
文化祭で配る栞の印刷を頼むことから、活版印刷の出張ワークショップへと話が広がり・・・。
先生と生徒たちの心の交流を描く佳作。
4. ひとつだけの活字 (第一巻 第四篇)
大西君の1年先輩である、わたし(図書館司書の佐伯雪乃さん)の物語。
幼なじみで大学同期の宮田友明との結婚を控え、準備に忙しい。
大西君を通じて三日月堂を知り、結婚案内状を祖母の持っていた少数のひらがなのみの活字
で作成したいとの希望を、弓子さんに告げる・・・。
弓子さん自身の過去、弓子さんが幼いころに亡くなった母カナコさんと父とのエピソード、そして父親の死。
それぞれの過去から現在、そして未来への人々の思いがいっぱい詰まった物語です。
すてきな本にまた出合えました。
以下紹介です。
活版印刷三日月堂(第一巻 星たちの栞)
著者 ほしおさなえ
川越の街の片隅(鴉森稲荷神社の近く)にある活版印刷所のお話。
かつてその印刷所を営なんでいた祖父の後を継ぐことになった月野弓子さんと、周りの人達との心温まる短編集
(短編集と言っても語り手が変わりながら三日月堂にまつわる話の連鎖です)。
文章が落ち着いていて美しくわかりやすい。
登場する人達の心の動きが丁寧に描写されています。
宮下奈都さんの作品と同じような読後感でした。
(もう少しほっこりとした優しい感じかな)
続編が読みたくなる物語です。
1. 世界は森 (第一巻 第一篇)
三日月堂を再開することになったきっかけのお話。
わたし(市倉(旧姓藤山)ハルさん(川越運送店一番街営業所 所長))と、この春大学生になり家を出てゆく森太郎君の物語を軸に、
ジョギング仲間の、柚原さん(観光案内所のスタッフ)、大西君(大学院生、観光案内所のバイト)、葛城さん(ガラス店兼工房経営)
が登場。
ハルさんから森太郎君への卒業祝いである、名入りのレターセットのお話。
『名前って、不思議だな』・・・。
母子のきずなと、人々のやさしさに涙します。
2. 八月のコースター (第一巻 第二篇)
川越一番街のはずれで、喫茶店『桐一葉』を経営している僕(岡野まあ君)の話。
伯父から引き継いだ喫茶店の経営について、伯父の個性、自分の個性について悩む。
ハルさんから三日月堂のことを聞き、弓子さんとともに伯父の『短歌』を印刷したオリジナルコースターをつくる。
伯父はまあ君に俳句の手ほどきもしたことがあり、店名の桐一葉も高山虚子の句だった・・・。
まあ君は大学の俳句部に在籍していたことがあり、当時一緒にいた原田さんのことを思い出す。
伯父時代からの常連とのやり取りやまあ君の決意が胸に迫ります。
3. 星たちの栞 (第一巻 第三篇)
わたし(遠田先生、鈴懸学園の国語教師)と文芸部の生徒たち、村崎小枝、山口ゆう加の物語。
桐一葉でコース―たーを見た遠田先生が、生徒たちと三日月堂の見学に行く。
文化祭で配る栞の印刷を頼むことから、活版印刷の出張ワークショップへと話が広がり・・・。
先生と生徒たちの心の交流を描く佳作。
4. ひとつだけの活字 (第一巻 第四篇)
大西君の1年先輩である、わたし(図書館司書の佐伯雪乃さん)の物語。
幼なじみで大学同期の宮田友明との結婚を控え、準備に忙しい。
大西君を通じて三日月堂を知り、結婚案内状を祖母の持っていた少数のひらがなのみの活字
で作成したいとの希望を、弓子さんに告げる・・・。
弓子さん自身の過去、弓子さんが幼いころに亡くなった母カナコさんと父とのエピソード、そして父親の死。
それぞれの過去から現在、そして未来への人々の思いがいっぱい詰まった物語です。
2018年03月21日
宮下奈都さん
『羊と鋼の森』に続いて、『窓の向こうのガーシュイン』を読みました。
早産で小さく生まれた女の子が、少しずつ少しずつ成長してゆく話です。
羊・・・の主人公外村君と同様、窓・・・の主人公佐古さんも自分の人生を
まっすぐに歩いてゆく人なのでした。
そして周りの人達も優しくて、でも現実は厳しくて。

佐古さんは、人々の話や主張に単にうなずいてやり過ごすことで、波風立てずに生きてきたけれど、自分の気持ちを抑えて考えないように、思い出さないように生きてきたけれど、ある時素直な自分の気持ちの発露を受け取ってくれる人たちがいることに気づく。
そのような人達と会って話すこと、一緒にいる事に小さなしあわせ、わずかな希望を感じる。
しかしそれを『しあわせ』としっかり認識をしてしまうことへの恐れを拭い去ることができない・・・。
佐古さんがしあわせな気持ちのまま暮らすことができるようになり、家族や周りの人たちと歩いてゆく先にも良い事がありそうな予感に包まれて終わるこの物語は、ハッピーエンドであっても人とは何かと考えてしまい、胸がとっても切なくなる物語です。
ガーシュインのサマータイムも良い味を添えてくれていますよ。
(外村君も佐古さんもファーストネームが出てきません。 物語には全く影響しないのですが(だって此の事にしばらく気が付きませんでした)、このような小説は初めてです。)
物語には全く影響しないのですが(だって此の事にしばらく気が付きませんでした)、このような小説は初めてです。)
宮下奈都さんの感性が大好きです。
次は『神様たちの遊ぶ庭』、『スコーレNo.4』に取り掛かります。
早産で小さく生まれた女の子が、少しずつ少しずつ成長してゆく話です。
羊・・・の主人公外村君と同様、窓・・・の主人公佐古さんも自分の人生を
まっすぐに歩いてゆく人なのでした。
そして周りの人達も優しくて、でも現実は厳しくて。

佐古さんは、人々の話や主張に単にうなずいてやり過ごすことで、波風立てずに生きてきたけれど、自分の気持ちを抑えて考えないように、思い出さないように生きてきたけれど、ある時素直な自分の気持ちの発露を受け取ってくれる人たちがいることに気づく。
そのような人達と会って話すこと、一緒にいる事に小さなしあわせ、わずかな希望を感じる。
しかしそれを『しあわせ』としっかり認識をしてしまうことへの恐れを拭い去ることができない・・・。
佐古さんがしあわせな気持ちのまま暮らすことができるようになり、家族や周りの人たちと歩いてゆく先にも良い事がありそうな予感に包まれて終わるこの物語は、ハッピーエンドであっても人とは何かと考えてしまい、胸がとっても切なくなる物語です。
ガーシュインのサマータイムも良い味を添えてくれていますよ。
(外村君も佐古さんもファーストネームが出てきません。
 物語には全く影響しないのですが(だって此の事にしばらく気が付きませんでした)、このような小説は初めてです。)
物語には全く影響しないのですが(だって此の事にしばらく気が付きませんでした)、このような小説は初めてです。)宮下奈都さんの感性が大好きです。
次は『神様たちの遊ぶ庭』、『スコーレNo.4』に取り掛かります。

2018年03月10日
『小説』って?
今回も読んだ本の話。
『羊と鋼の森』、大変面白い、いや新鮮です。
心を揺さぶられるのか、掴まれるのか。
主人公、戸村(とむら)くんの生きて行く歩みに大いに感情移入してしまう。
彼のこころの正直な持ちようと、彼を取り巻く人達のなんて言うか、真摯なやりとり。
この様な本が、ジャンルが、小説があったんだと久し振りに気がつかせてもらいました。
振り返ってみれば最近読む本は、実用書だったり、サスペンスだったり、SFだったり……。
ひさびさに『小説』というものを読みたいへん『感動』致しました。
ピアノに興味があるからだったかもしれない。音楽に興味があるからだったかもしれない。
でも彼の細やかな感情の揺れや素直な(感情の)表現。
作者、宮下奈都さんが余すところなく表現していると思います。
有難うございました。この様な本に出会えて幸せです。
(このためやらなくてはならない仕事が少し遅れました。(笑))
P.S.
音楽ジャンルのマンガ、特にピアノでは『ピアノの森』と『ピアノのムシ』が
面白かったですね。
特にピアノのムシは、調律師の話なのでかぶるところが多かったな。
続きを読む
『羊と鋼の森』、大変面白い、いや新鮮です。
心を揺さぶられるのか、掴まれるのか。
主人公、戸村(とむら)くんの生きて行く歩みに大いに感情移入してしまう。
彼のこころの正直な持ちようと、彼を取り巻く人達のなんて言うか、真摯なやりとり。
この様な本が、ジャンルが、小説があったんだと久し振りに気がつかせてもらいました。
振り返ってみれば最近読む本は、実用書だったり、サスペンスだったり、SFだったり……。
ひさびさに『小説』というものを読みたいへん『感動』致しました。
ピアノに興味があるからだったかもしれない。音楽に興味があるからだったかもしれない。
でも彼の細やかな感情の揺れや素直な(感情の)表現。
作者、宮下奈都さんが余すところなく表現していると思います。
有難うございました。この様な本に出会えて幸せです。
(このためやらなくてはならない仕事が少し遅れました。(笑))
P.S.
音楽ジャンルのマンガ、特にピアノでは『ピアノの森』と『ピアノのムシ』が
面白かったですね。
特にピアノのムシは、調律師の話なのでかぶるところが多かったな。
続きを読む
2018年03月08日
大好きな読書:イントロ
久しぶりの投稿です。

書きたいことはいっぱいあるのだけれど、構えてしまいます。
自然体、自然体。

読書が好きです。いろいろ手当たり次第に読みます。(若い時は)
現在はそれでもジャンルが絞られてきたかな。
活字も、マンガも好みます。
本日はジャンルをまとめてみたく。
① 推理小説
② 科学NF(数学、量子力学、科学史、アシモフetc.)
③ 戦記物
④ SF
⑤ 歴史小説
まとめたい事は、ジャンルではないなぁ。

いつか具体的に書名を羅列したいですね。
(そうか、分かった。読書の自分史をつくりたいのだな。今わかりました。 )
)
 )
)とりあえず本日はアンディ・ウィアーです。
『アルテミス』、ただいま読了。
たいへんおもしろかったです。プロット、語り口、リアリティ(これは大事:近未来の月面の話なので)が良いですね。
科学全般(特に物理学)をよく知っている感じがガンガン伝わります。
『まるほど!』という感じ。
アシモフさんにも通じるかな。
アンディさんは『アルテミス』が二作目だったのですが、一作目の『火星の人』(映画『オデッセイ』の原作ですね。)もおもしろかった。

現実に起こりうる出来事を、ありそうな(あるはずの)出来事として、科学的に矛盾の無い展開をつづっています。
合理的、クールですかね。
次作も期待!!。
並行して、『般若心経』を読んでいます。
おもしろいけどしっかり読まなくてはなりません。(飛ばし読み不可:当然!)
そこで気になっていた、『羊と鋼の森』にも取り掛かりました。
心の内なる旅路への予感です。
おもしろそう。

感想はまた後日。

以上